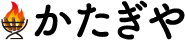薪ストーブに最適な薪の太さとビール瓶の関係
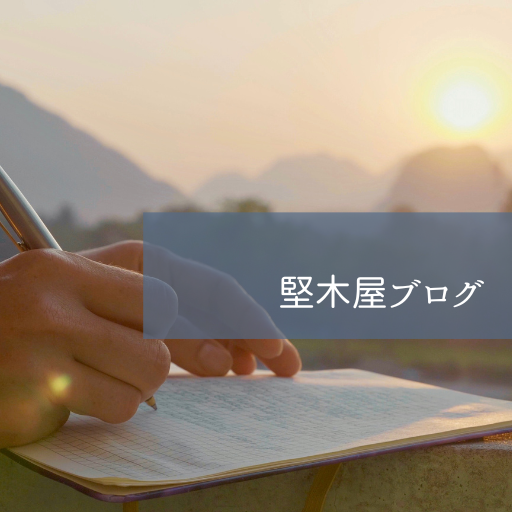
薪ストーブに欠かせない薪。
原木の伐採から始めて薪を作る人、玉切り薪から斧で薪割りする人、いろんな方法があると思います。
では、薪ストーブの性能を最大限に引き出す薪の太さって、どんなサイズだと思われますか?
それは、
「ビール瓶小瓶から大瓶」
くらいなんです。

「いやいや、両手でやっと持てるくらいのメガ薪が何度も薪をくべなくてよいので効率的ですよ。」
と言うユーザーさんも多いと思います。
ところが、メガ薪を完全に燃焼させるには薪ストーブは薪の中心部に向かって絶えず熱を供給しなければなりません。
この熱は周辺の燃焼熱によって得られるわけですから、薪外部の温度は次第に低下してきます。
結局、加速度的に温度が低下していき、薪がくずぶり煙が出はじめます。
これを再び燃やすために、ダンパーを開けたり扉を開けたり、細い薪を投入したりしなければなりません。
私も住宅密集地で薪ストーブを焚いていますが、くずぶり始めるととても焦ります。
ところで、ここで火災現場の映像を思い出して見ましょう。

家財は全て燃え尽きていても、家の構造材である柱や梁はしっかりと残っていますよね。
柱の寸法は、10.5センチ角(3寸5分角)以上と決まっています。つまり、これくらいの寸法となると、あの高温灼熱の世界でも燃え尽きることが難しいということなんです。
そしてもう1点、メガ薪の問題は乾燥しにくいということです。
薪の乾燥は、おおむね断面積の大きさの2乗に比例して進みます。
例えば、直径3センチの薪が3ヶ月で乾燥するとします。
すると、直径6センチの薪は直径が2倍なので、2×2×3ヶ月=12ヶ月=1年が乾燥期間となります。
直径9センチとなると、3×3×3ヶ月=27ヶ月=約3年も必要となります。
逆に、細すぎる薪は一気に高温にはなりますが、何度も薪を足さなくてはなりません。
もちろん、薪の断面をきっちりビール瓶の直径にそろえるということは無理ですので、1年から2年を目安にして乾燥期間をとれば許容範囲ということになります。
ちなみに、ビール瓶の直径は、小瓶が61ミリメートル、大瓶が77ミリメートルだそうです。
今回は、薪の太さについてご説明しましたが、薪の乾燥にはそれ以外にも保管する場所や積み方などたくさんの要因が絡んできます。
それらにつきましては追ってご紹介いたします。